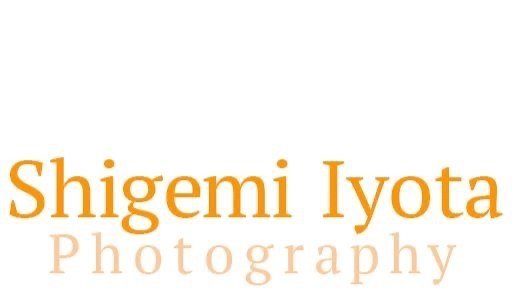24歳の時に暮らしたケニアをはじめ、子どもが生まれるまでアジアや南米で旅していたのは観光客があまり行かない場所、日本でいうとまさに今住んでる土佐町みたいな場所ばかりだった。いろんな国の普通の人の暮らしに触れたい、そこでバックグラウンドや人種が違っても人として共感し合えるものを感じたい、そんな人間への興味からだったと思う。
写真をたくさん撮ったし、どこに行っても子ども達の写真を撮るのは大好きだった。でもよく言われる「途上国の子ども達は貧しいけど笑顔が輝いている」というフレーズには違和感があった。「貧しい」と「笑顔」の結びつけ方に解像度の低さを感じ、先進国に住んでる自分たちの傲慢さをどこかで感じてたからだと思う。
いま写真を整理してて、やっぱり子どもの笑顔は輝いているなぁと思う。命が喜んでいる時、内側がそのまま外側がつながってはじける笑顔になる。
命が喜ぶのは、小さな自分の外にある世界にリアルに触れたり、自然の輝きに触れたり、自分以外の命あるものに出会い五感が稼動する時。
途上国では、そんな機会が圧倒的に多い。逆に日本の子どもたちは清潔さや安全と引き換えにそういう機会をずいぶん取り上げられているなぁと思う。その上、すでに消化しきれないほどの情報に囲まれて、心が躍動しにくくなってるのは大人だけではない。
前回に引き続き、渡貫家の話になるのだけど、先日「採蜜するからおいでよ」と呼んでもらって写真を撮った。うちの実家でも最近父がやっていて、帰ると立派なハチミツを持たせてくれるのだけど、実際どんな風にハチミツが取れるのかを見たことはなかった。渡貫家の父ちゃんが巣箱をバラしてハチミツを取り始めると、子どもたちがわらわらと集まってきた。たまりかねたように1人が指を突っ込むとわれもわれもと5人5本の指が行き交う。「もうやめなさい!」と言われる前に突っ込めるだけ突っ込んどこうという気持ちが溢れ出てる。「普段ならこんなには許さないけど、写真撮ってるから写真スペシャルやぞ」という父ちゃんの言葉にしめしめ、「にまぁ」と笑って、「ウマいね、ウマいね」と指を突っ込む。
自分たちでは何も手を加えないのがコンビニのお弁当だとして、それ以前のステップに触れることが出来る日常には、たくさんの喜びと笑顔が溢れている。料理をするために、薪で火を起こす母ちゃんを毎日見ている渡貫家の子どもたちは、食事前に必ず揃って手を合わせる。食べれることへの感謝。「嬉しい。ありがとう」という気持ち。誰かが自分のために時間をかけて作ってくれた食べ物には、ダイレクトでわかりやすい愛情が宿っている。先進国では、みんな忙しいからなるべく手間を省ける食べ物が人気だし便利だし、だからコンビニもすごい数。でも、巣箱から出てきたハチミツに指を突っ込める喜びは売っていない。
欲望に歯止めをかけるのが不得意な私たちは、世界の富の半分を世界人口のわずか1%の億万長者や富裕層が保有するアンバランスな世の中になっても、それを成功の形だと信じ込んでる。ーーーでも。もっともっと、という欲望の果てに、どれだけのしあわせが残っているのかな。
いろんなものが無限にスーパーに並んでいて手に入るのは当たり前ではなく、本当はそんな必要もないこと。小さな巣箱のハチミツを競い合って舐めた思い出と一緒に、子どもたちにはそんな思いも育っていくだろう。それは素敵な希望の光。先進国にも宿る、個から始まるそんな小さな希望の光を、私も写真と一緒にすくいあげていきたい。